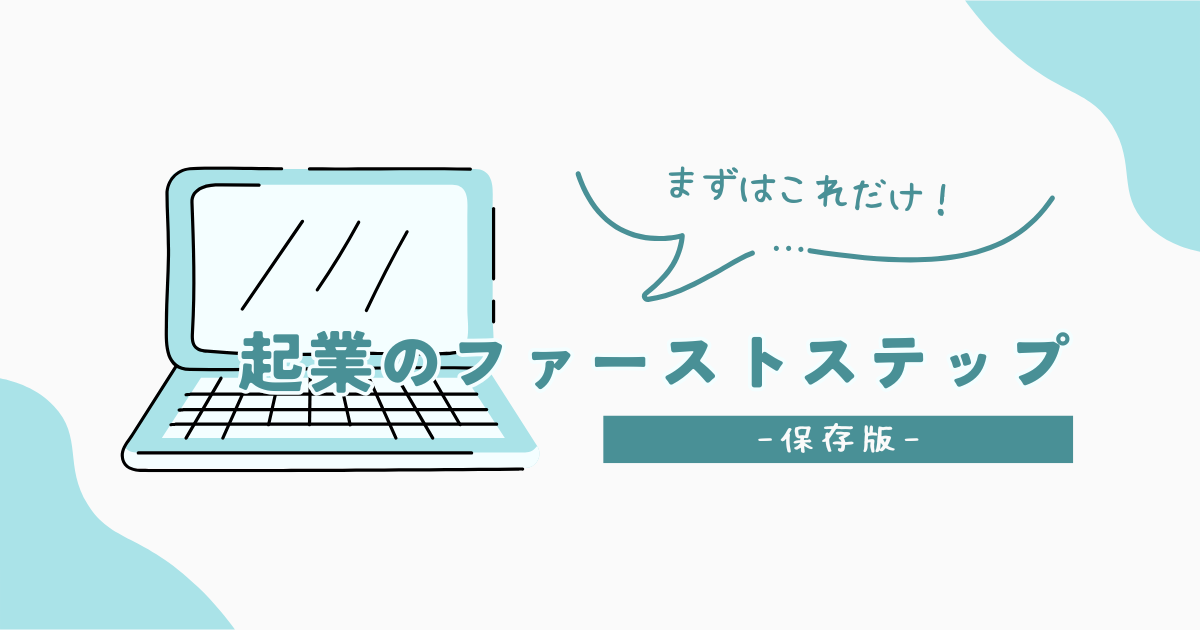「起業したいけど、何から始めればいいの?」
そう思ったとき、私がまず考えたのは時間やお金をかけすぎず、必要最低限で始めることでした。
当時は、子育てに加えて長期療養中の家族のケアもしていて、動き回ることは難しい状況。だからこそ、家からでも手続きできる方法や、初期費用を抑える工夫を試行錯誤しながら見つけてきました。
この記事では、そんな私の体験をふまえて、「個人事業主として起業するために、最初に整えておきたい準備」について紹介します。
✔ 事業用の口座の準備
✔ 住所や連絡手段をどうするか
✔ 無料でも使えるツール紹介
✔ 信用につながったもの、あとから整えたものでよかったもの
これから起業を考えている方にとって、無理なく始めるヒントになれば嬉しいです。
起業前に考えておきたいこと
本格的に起業準備を始める前に、自分にとって「ちょうどいい働き方」はどんなものかを整理しておくことをおすすめします。特に私のよに自主的な働き方改で起業するのであればなおさらです。
家族の状況や生活スタイルに合わせて無理なく続けられる形を見つけることが、長く続けるための土台になります。
働き方と生活のバランスをどう取るか
起業は、自分の暮らしと仕事をどう調和させるかを考える絶好のタイミングです。
私自身、起業当初は子育てに加えて、長期療養中の家族のケアがありました。
限られた時間の中で、どうすれば仕事が回るかを何度もシミュレーションしました。
「日中どれくらい仕事に使えるのか」
「急な対応が必要な家族のことはどうするのか」
こうした視点でスケジュールを想定し、無理のない働き方を考えることが大切です。
起業は自由なようで、すべて自己責任です。だからこそ「最初に自分にとって現実的な働き方をイメージしておくこと」が、無理なく続けるコツになります。
仕事のスタイルと必要なツールをイメージする
起業準備では、事業内容に応じた「必要なツールの見極め」も重要です。
私は専門職のBtoBコンサル業で独立したため、大掛かりな設備投資や原料の確保などは不要でしたが、資料の作成、連絡手段の確保、見積書や請求書の発行といった基本的な体制は整える必要がありました。
事業のスタイルによって必要なものは変わります。たとえば・・・
-
オンライン完結型:パソコン・チャット・会計ツールなど最低限でOK
-
対面サービス:名刺・連絡先・事業用住所・信頼感あるHPが必要
-
物販:ホームページや連絡先の開示が必須(特商法対応)
「どんなやり方で、誰と、どのくらいの規模で仕事をするのか」を考えながら、準備を無駄なく進めるとコストも抑えられます。
最初から全部そろえなくてもいい理由
起業するとなると色々と準備が必要になりますが、一気にすべて整える必要はありません。
私自身も、必要なものを段階的にそろえていく形でスタートしました。
最初に取りかかったのは、独自ドメインの取得とホームページの作成です。
費用が気になって一度は躊躇しましたが、「ホームページは最初に作っておいた方がいい」という、先に起業した知人からのアドバイスに納得し、真っ先に着手しました。
起業した地域にはコネクションが一切なく、自分の事業を知ってもらうツールが必要だったことも大きな理由です。
そのため、信用構築と情報発信を兼ねてまずはホームページを自作しました。詳しい方に相談しながら、コーポレートサイトはエックスサーバーで運用しています。
独学だったのでかなり時間はかかりましたが、今でも「最初に作っておいて本当に良かった」と感じています。
外注する場合は費用がかかるため、収益の見込みや予算に応じて判断すれば大丈夫です。
ホームページが完成したタイミングで開業届を提出。
いよいよ営業も始めることになったため、事業用の携帯番号と名刺を用意しました。バーチャルオフィスの契約も、届を出した直後くらいの時期です。
その後は、屋号付きの口座を開設し、連絡手段としてチャットツールを導入。
さらに、対外的な信用を意識して、固定電話番号(03plus)も整えました。
事業を始めた後に必ず必要になる帳簿については、個人事業主時代は会計ソフトを使わずに対応しました。
私の業種は専門型のコンサル業で、原価や仕入れがなく仕訳もシンプルだったため、青色申告の解説書に付いていたExcel帳簿で十分でした。
確定申告もそのまま対応でき、特に困ることはありませんでした。
ただし、仕訳が複雑な業種や、申告に不安がある方には会計ソフトの導入をおすすめします。
使わないにしても、まずは会計や青色申告の基礎がわかる本を1冊読んでおくと安心です。
開業準備チェックリスト|最低限のスタートに必要なもの
起業準備と聞くと、特別な道具や高額な設備が必要に感じるかもしれません。
ですが、個人事業主としてスタートするなら、本当に必要なものは意外とシンプルです。
ここでは、私が実際に整えてきた中で「これは最初に用意しておいてよかった」と思えたものを、厳選してご紹介します。
名刺と連絡手段は最優先で整える
開業を決めたら、まず必要なのが名刺と事業用の連絡手段です。
ホームページを先に作ったとはいえ、実際に営業を始めるタイミングでは「直接のやりとり」に使えるものが必要になります。
もちろん、プライベートの携帯番号をそのまま使っても問題ありません。
ただ私は、事業とプライベートをしっかり線引きしたかったことと、経費にする場合に「按分」を考えるのがややこしく感じたため、携帯をデュアルSIMにして番号を使い分ける方法を取りました。
DTI SIMやNUROモバイルを経て、今はpovoを使っています。povoは月額0円から始められるので、初期の負担を抑えたい人にもおすすめです。
現在は格安SIMの種類も非常に豊富なので、通話が多い方・データ通信量が多い方など、ご自身の使い方に合わせて最適なプランを選んでください。
名刺は、単に連絡先を渡すだけでなく、営業ツールとしても非常に有効です。
私はホームページとセットで活用していて、名前・肩書き・連絡先といった基本情報に加え、QRコードやサービスの簡単な紹介も記載しています。
営業時や打ち合わせの場で自然にホームページを紹介することもでき、大活躍しています。
「とりあえず事業を始める」なら、名刺と連絡手段の整備が最優先で十分。
どちらも初期費用は抑えられるため、手を付けやすい準備物のひとつです。
ホームページは「作るかどうか」より「いつ作るか」
起業を考えた時に悩むのが、「ホームページは必要なのか?」ではないでしょうか。
結論から言うと、必要かどうかではなく、“いつ作るか”を最初に決めておくのがおすすめです。
特にBtoBの事業で士業ではなければホームページは必須だと思います。
toCであれば、インスタグラムなどのSNSでも代用可能ですし、戦略次第ではそちらの方がいいかもしれません。
私は、起業を先に経験した知人から「ホームページは早めに作っておいた方がいい」と言われ、真っ先に取りかかりました。
というのも、私の場合は起業した地域にまったくコネクションがなかったため、自分の存在や事業を知ってもらうための媒体がどうしても必要だったからです。
実際の制作は独学で行い、わからない部分は詳しい方に相談しながら、エックスサーバーを使って立ち上げました。
時間はかかりましたが、話のネタにもなりますし、新サービスの開始なども自分のタイミングで発信できるのは大きな強みです。
ホームページは、信頼感・事業内容の整理・問い合わせ導線の整備にもつながるため、早めに整えておくのがベターです。実際に、ホームページの問い合わせから連絡をいただき、受注につながっているケースもあります。
一方で、すでに紹介やつながりから受注が見込める場合などは、予算をある程度確保してから外注するのもひとつの手です。
作るかどうかを悩むよりも、「いつ・どの段階で・どれくらいの予算で作るか」を決めておくことが、無駄のない準備につながります。
住所の扱いは慎重に|バーチャルオフィスという選択肢
起業にあたって、意外と見落とされがちなのが「事業用の住所をどうするか」という問題です。
ホームページに記載するほか、物販などを行う場合は、特定商取引法の観点から住所や電話番号の公表が義務づけられています。
ホームページを作成するにあたり、色々なコーポレートサイトを確認しました。
その中で「会社の情報」が必ず掲載されていることに気づき、もしかして表示義務があるのでは?と思い調べたところ、特定商取引法によって詳細が定められていることを知りました。
この「特定商取引法に基づく表記」は、法人だけでなく個人事業主にも同じ義務があります。
屋号やビジネスネームではなく、本名・現住所・電話番号の記載が必要になるという点は、意外と知られていない印象です。
では、コンサル系などのサービス業ではどうかというと、ホームページからそのままサービスの申し込みや決済ができる形であれば、基本的には表示が必要です。
逆に、「お問い合わせのみ」で契約まで進められない場合は、厳密には表示義務の対象外になるとも言われています。
ただ、私は「販売要素がある以上、表記しておくべき」だと考えています。
自分が購入者側であれば、ホームページに住所や連絡先の記載がないと怪しく感じます。
事業の信頼性を高める意味でも、たとえ法的に義務がなくても商取法に準じた情報を掲載することをおすすめします。
私自身、自宅住所をネット上に出すことには抵抗があったため、バーチャルオフィスを利用することにしました。
ホームページに記載する住所としてだけでなく、名刺や請求書にも使え、信用構築の一環として非常に役立っています。
現在は、コワーキングスペースを一定時間利用できるプランがあるエキスパートオフィスを利用していますが、
自宅やカフェで作業するのであれば、完全なバーチャルオフィスで問題ないと思います。
私自身も、コワーキングスペースの利用機会が少ないこともあり、完全なバーチャルオフィスに切り替えようか検討中です。
バーチャルオフィスのメリットは以下のとおりです:
-
自宅住所を公開せずにすむ
-
一等地の住所を使用でき、対外的な印象が良くなる
-
郵便物の転送や電話番号オプションなど、必要に応じて機能を追加できる
一方で、すでに紹介やつながりで受注がある方や、ネット上で住所を公開しないスタイルでも成立する事業の場合は、自宅住所で届出だけして、公開は避けるという方法もあります。
いずれにしても、ご自身の事業スタイルに応じて、住所をどう扱うかは早めに決めておくのがおすすめです。
私のようにホームページを作るけど自宅住所の公開は抵抗があるという場合は、バーチャルオフィスが安心感と信頼感のベースになってくれます。
個人口座でもOK?屋号付き口座は必要に応じて検討を
起業にあたって「屋号付きの銀行口座は必要か?」という疑問が出てくるのではないでしょうか。
要否で言えば、個人口座であっても事業用に利用することはできるため、必ずしも屋号付き口座を作らなければならないというわけではありません。
ただし、「事業用の名義で新たに口座を作る」場合、個人事業主であれば開業届の控えなどが必要になります。
私の場合は、開業届を提出したあと、すぐに屋号付きの銀行口座を開設しました。
とはいえ、事業開始直後は実際の入出金が少なかったこともあり、急いで作る必要はなかったなというのが正直な感想です。
一方で、すでに起業時点で受注が見込めている、あるいは顧客がいるという方であれば、早い段階で口座を分けておくことで、お金の流れが非常に整理しやすくなります。
屋号付き口座を作るメリットには、以下のような点があります:
-
事業とプライベートの資金を明確に分けられる
-
請求書や名刺に記載でき、信用につながる
-
帳簿管理がより楽に、かつ明瞭になる
とはいえ、口座がひとつ増えることで管理の手間が増えるという面もあります。
もしあまり使っていない個人口座がある場合は、「これは事業用として使う」と決めて流れを分けておくという方法も、十分実用的です。
事業の規模やスピード感に応じて、自分にとって扱いやすい方法を選ぶのが良いと感じています。
屋号付き口座の開設方法やおすすめの銀行については、別の記事で詳しくご紹介しています。
続きを見る
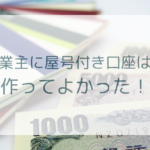
事業用に銀行口座は分ける?私が屋号付き口座を開設した理由
ツールは使いながら選ぶ|【最初に用意したもの】連絡ツール、スケジューラー、会計ソフト
起業準備の中で、何をどこまで整えるべきか迷うのが、事業運営に欠かせないさまざまなツール。
中でも連絡ツール・スケジューラー・会計ソフトは、できるだけ早い段階で検討しておくことをおすすめします。
今でこそ多くのツールを使っていますが、最初からすべてを完璧にそろえていたわけではありません。
私はまずこの3つを決めて、その他は必要になったタイミングで少しずつ整えていきました。
ここでは、私が起業初期に実際に用意した「連絡ツール・スケジューラー・会計ソフト(的な仕組み)」をご紹介します。
連絡ツール|メール+Chatwork
お客様とのやり取りには、メールに加えてChatworkも使用しています。
最初は無料プランを使っていましたが、現在はチャットを使ったサービス提供を行っていることもあり、有料プランに切り替えました。
無料プランでは、40日以上前のチャット履歴が削除されてしまうという制限があります。
ただし、顧客とのやり取りがファーストコンタクト中心であれば、無料でも十分使えると思います。
LINEは気軽ではありますが、個人との境界が曖昧になりやすく、セキュリティ面も気になるため、私は事業では使用していません。
Chatworkは、公私をしっかり分けたい人にとって、安心して使える連絡ツールだと感じています。
スケジューラー|Googleカレンダーで一元管理
起業当初、私は仕事とプライベートの予定を別々のカレンダーで管理しようとしていました。
スマホにスケジューラーアプリをいくつか試してみたのですが、当然のことなのですが、「同じ時間に予定は重ねられない」ことに気づき、ひとつのカレンダーで管理する方が合理的だと感じました。
そのなかで今も使い続けているのが、Googleカレンダーです。
Googleカレンダーは、ひとつのアカウント内に複数のカレンダーを作成できるので、プライベートと仕事の予定を分けて管理しやすいのがメリット。
予定の種類ごとに色分けができるので、仕事・プライベート・家庭の予定などがひと目で区別できます。
この仕組みが、仕事とプライベートを分けて管理したいけど同時に把握したいという一見相反する私の希望にピッタリでした。
実は私は文房具好きでもあるので、手帳も併用していますが、予定管理という点ではGoogleカレンダーがメインです。
アカウントを複数作る必要もなく、スマホやPCとスムーズに同期できる点も含めて、Googleカレンダーは、スケジューラーとして非常におすすめできるツールです。
会計ソフト|実はExcel帳簿でも問題ない
起業と同時に「会計ソフトを導入しないといけないのでは?」と思う方も多いかもしれません。
ですが、取引の内容がそれほど複雑でなければ、Excel帳簿でもまったく問題ありません。
私自身、個人事業主として開業した当初から、会計ソフトは使わずにExcelで帳簿を管理してきました。
というのも、私の事業は専門型のBtoBコンサルで、原価や在庫管理が必要なわけでもなく、使用する仕訳も少なくシンプルだったからです。
このとき使用していた帳簿は、「超シンプルな青色申告、教えてもらいました!」という書籍に付録でついていたExcelテンプレート。
この本は、「まずは簡単な青色申告の本を1冊読んでおくといいよ」とアドバイスされ、私が最初に手にとった本です。
その名の通りシンプルで、公認会計士が作成したテンプレート付きという点も心強く、スムーズに帳簿管理を始められました。
ただし、仕訳が多くなったり、売上規模が大きくなってきたりすると、会計ソフトの導入は検討した方がよいかもしれません。
実際、法人化してからは会計内容もより詳細になったため、現在は会計ソフトを使っています。
freeeやマネーフォワードなど、簿記知識がなくても使いやすいソフトも多く出ているので、自分の事業に合ったものを無理のない範囲で選ぶとよいと思います。
まとめ
起業準備というと、「開業届をいつ出すか」といった形式的な枠組みやステップに目が向きがちです。
もちろんそれも大切ですが、実際に事業を始めてみると、それ以外にも細かな選択や準備が必要になると感じました。
私も起業初期は、必要最低限の準備に絞ってスタートしました。
限られた時間と労力の中で決めることばかりだからこそ、「自分の事業にとって何が必要か?」を見極めることがとても大切だったと思います。
今回ご紹介した内容も、「最初から全部そろえるべき」ではなく、事業内容や展開のタイミングに応じて、優先順位をつけて選ぶことがポイントです。
-
ホームページはすぐに必要か?
-
名刺や連絡手段はどこまで整えるか?
-
会計はどう管理するのが自分に合っているか?
起業のかたちは本当に人それぞれ。
大切なのは、「他の人がやっているから」ではなく、「自分の事業に合う準備」を選ぶことです。
この記事が、これから起業を考える方にとって、等身大のヒントになればうれしいです。